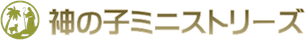No.2 聖書台本の深み
清水英子
聖書のメッセージを伝えることができる腹話術は素晴らしいツールです。ある人が言ってくれました。「腹話術は柔らかくていいですね。」そうなのです。人々は人形が登場すると驚き期待します。しーんとして、人形は何をしゃべるのだろう?と興味津々です。集中して心を開いて聴いてくださる。そこに神さまの愛を届けることができるのです。
神が愛を一方的に届けてくださるのは人間が自分を救うことができないからです。ですから、人の弱さ、葛藤、愚かさ、飢え渇きなどを台本に込めなくては説得力がありません。あらすじでは心の深みを伝えることができないのです。
めぐみ先生からはたびたび「ザアカイはどんな飢え渇きを持っていたのか?」「羊飼いはどんな葛藤をもって生きていたのか?」と問われました。「ああ、やっぱり。わたしはそこが分からないのだなぁ。もやっとしたまま話を作っているのだ」と頭を抱えます。聖書や絵本の登場人物の気持ちにならないと作ることができない台詞や表現があるのです。
ザアカイなら、いじめられて金の亡者になった。でも心が乾いてどうしようもない。イエスさまとの出会いによって飢え渇きが癒され喜びが爆発する。似たような気持ちになったことがあるのでは?自分の限界を知ったことがありました。そうそう、神さまの愛がわかったときは感動で心が震えたなど。書いては消しアドバイスをいただいては直しの作業が続きます。何度か書き直して先生からOkが出るとほっとして勇んで練習し、実演します。
そこからまだ、道は続くのですから奥が深いです。台本ができて台詞が決まってから表現力を磨くという段階があるのです。人形の動きと間とリズム(とんとんと進むところとゆっくりになるところ)、そしてストーリーの山場をどう表現するか。
演劇の世界では、俳優は「この台詞をどのように言うかたくさんのパターンを考える。相手がこう来たらこう返す。または共演者や演出家にその場面で表したいことを話し合って決める」と聞きました。演じるとはこういう積み重ねなのだと納得しました。人形の台詞をああだこうだと言い方を変えてみたり、何がふさわしいのか考えるのはとても面白いです。
腹話術はほんとうに楽しいです。子どもたちにも喜んでもらえます。「〇〇ちゃーん!」と歓迎してくれます。行かないと「〇〇ちゃん、きょう来てないの?」と聞かれます。動くだけで笑ってくれることもあります。「どうしてここで笑ってくれるの?うーむ、わからないけれど嬉しい。」大人の方からは「感動した」と言ってくださることがあり、励まされます。これからも少しずつ聖書台本に挑戦したいです。