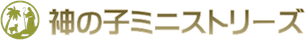No.3 聖書台本奮闘記
佐藤 敬子
ゴスペル腹話術の例会に参加して20年近くになります。ここまで長く続けられたのは、技術的な向上を求めたからと言うより、先生のお話やメンバーとの交わりが、とても楽しく有意義のものだったからです。
とは言うものの、2011年から始まった「腹話術霊想」は毎回ゴスペル腹話術の基本をしっかり学び直す機会となりました。その中でも「聖書台本がメッセージとなるために」の7回シリーズは、私に多くの気づきと反省を与えてくれました。特に“聖書台本は、物語のアウトラインをなぞってはいけない”という文章が心に刺さりました。
私は長い間「術者は話のあらすじを語り、人形はそれに相づちをうち、最後に一言メッセージでまとめる」というパターンからなかなか抜け出せないでいたからです。「それがなぜいけないのか」もわかりませんでした。
しかし年月を重ねるうち、その台本は、「何か物足りない、つまらない」と思うようになり、どうしたら良いのか悩み始めたのです。
そのような時、この7回シリーズは「その原因はどこにあるのか」「どのようにしたら良いのか」をズバリ教えてくれました。
聖書台本を書く上で、一番初めにやらなければいけない大切な事は、術者自身がまずその聖書箇所からどのようなメッセージを神様から与えられたかをしっかり受け止める事でした。そして、その「霊的真理」を順序立てて整理する事だったのです。そのためには、十分時間をかけて神様の前にデボーションを持つ必要があります。
これは人形なしで語る説教者にも相通じる心構えだと思います。改めて聖書は、単なるお話ではなく生ける命の言葉なのだと示されました。
では、次にどのようにしてその「霊的真理」を術者と人形の会話に、振り分けていったら良いのでしょう。
今までのように人形が「うん」「そおー」と相づちを打つだけでは、済みそうにありません。そこで、私はこのシリーズの人形に関する3つの題目「人形の聖書理解」「血の通った人形の台詞」「キャラクターを育てる」に注目しました。真っ先に驚いてしまったのがこの題目の言葉なのです。
“人形の聖書理解ってどういう事?”
“人形のせりふが血の通ったものになっているか?”
“人形のキャラクターってなあに?”
などなど首をかしげる事ばかりです。
そして読めば読むほど自分がだんだん恥ずかしくなっていきました。
なぜなら、私は今までずーっと人形を単なる話を盛り上げるための道具(ツール)としか見ていなかったからです。
しかし、人形にも私と同じように独立した「意志」と「感情」があることを教えられました。うさ吉(人形の名前)は、さぞかし私の不当な扱いに悔しい悲しい思いを沢山味わってきた事でしょう。なのに一言も文句を言わず、黙ってついてきてくれたのです。思わず「ごめんね!」と謝りたい気持ちになりました。これからは、あの3つの題目を1つ1つ繰り返し学んでいきたいと思います。
「聖書台本がメッセージとなるために」への道のりは、限りなく長く思われます。でも聖書台本作りは、私の信仰を確かに養ってくれるし、人形のせりふと悪戦苦闘しながら考えていく時、そこにちょっとした“楽しさ”や“喜び”を感じるようになってきました。これは私にとってとても大きな変化なのです。
ですから、たとえ長い道のりでも一歩一歩進んで行こうと思います。