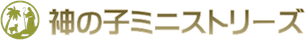No.5 歩き続ける
増田敏子
「あなたがたが、どのように歩いて神を喜ばすべきかをわたしたちから学んだように、また、いま歩いているとおりに、ますます歩き続けなさい。(口語訳聖書)」テサロニケ人への第一の手紙 4章1節
私がクリスチャンになってから初めて腹話術に興味を持ったのは、同じ教会の姉妹が腹話術のお人形を持っていて、日曜学校などで演じていたのを見た時からでした。パペットではなく、からくり式のお人形で、私の幼い娘は目や顎がカタカタ動くそのお人形を怖がっていました。本当にしゃべる(ように見える)、ある意味無表情な生き物に、娘は固唾をのんで、瞬きもせず見入っていました。それで私も、寝る前の読み聞かせなどでは、お人形は使わないまでも、登場人物の声色を変化させて読んでやったものでした。プリンセスの声、魔女の声、男の子、やまんば、動物、などなど、声を変えて大げさに読むだけで、登場人物が絵本から飛び出して立体的に子どもの想像の世界に入ってくるようで、子どもの知育に大いに役立つだけでなく、自分自身も楽しめました。子どもたちはそうして本好きにもなっていきました。
今と違い、夫が働き妻は専業主婦というケースが多い時代でしたので、ローンで家を建て、3人の子育てをし、子どもの成長につれ、義父母との生活と介護へ、というような生活を送ってきました。ちょっと他と違うところは、広い敷地と畑があるために何やかやと雑用があることと、キリスト教会での奉仕や交わりがあることでしょうか。夫の生まれた町に教会が建った時の同労者の一人として携わり、今日まで続けてこられたことはクリスチャンとしてとても幸いな歩みだったと感謝しています。
義母が亡くなった翌年の2011年9月に、腹話術師高橋めぐみ先生の腹話術講習会があるという情報を頂きました。かつて日曜学校教師訓練会で、めぐみ先生が何体もの人形を使ってドラマ腹話術というのを見せてくださったことを思い出し、参加してみたいという思いが湧いてきました。それが私のゴスペル腹話術参加のきっかけでした。その年は東日本大震災のあった年であり、ずっと以前からめぐみ先生から腹話術を習ってきた方々が、先生の数年間の休養のあと、新たに先生を交えてサークル活動を再開した年でもあったとのことでした。
それからの歩みですが、一言でいうと、腹話術がこんなに奥が深くて難しいとは思わなかった、ということです。教会の日曜学校で依頼したことのある腹話術の方々はほとんど、パペットが演者のせりふのオウム返しか、相づちを打つなどの、お決まりのやり取りのようだったと思います。それで腹話術は汎用的な台本を利用して、誰でも声さえ出ればすぐに演じることが出来るものだと思っていました。
ところが、発声から始まり、オリジナル台本作り、暗唱、人形と演者である自分の動きなど、ひとりで発案、脚本、俳優役に至るまで総合プロデュースしなければならない、とても大変な作業だと分かってきました。
一番苦労する台本作りは、聖書台本、絵本台本、証し台本など、先生からの課題に、生みの苦しみというほど努力をしてはいませんが、自分の能力の無さを痛感しました。暗唱については、若いころと違い、自分に腹が立つほど頭に定着しないもどかしさ。それで人形の動きに気を配るまで至らず、ありきたりの動きに留まる残念なありさま。セリフの裏にある人形と演者の感情の揺らぎや、それを裏付ける動作まで、細かく表現できたらいいなと思いつつも、出来ない、やらない、の自分よがりな言い訳。先生には不義理だけれど、もう辞めた方が楽、と思うことの連続でした。私よりずっと長く続けてきたメンバーは、よくやってきたものだと尊敬します。それ以上にめぐみ先生の、何体もの人形を駆使して1時間にも及ぶひとり舞台「ドラマ腹話術」は、いったいどれだけの時間と労力を掛けての作品だったろうかと、ただただ感嘆するばかりです。
それでも回を重ねるうちに、先生の励ましと忍耐をいただきつつ、メンバーの方たちの努力のパフォーマンスを見せていただけて、自分も頑張ろうと思いながら定例会の帰路に着く年月でした。
定例会での私の実演はいつも未完成で台本を見ながらの情けないものですが、もう13、4年何とか続いています。最近どこの教会でも日曜学校は減少傾向にあるようですが、数人の生徒の前で演じたり、クリスマスお楽しみ会で演じたりしています。それから他教会で演じさせていただいたことが数回。そしてこの2年ほど、県内のある小学校で芸術鑑賞会と称する子ども集会に出させていただく機会がありました。台本をどうするか迷いましたが、神さまというワードが入ることや賛美歌をパペットと歌うことについて主催者に尋ねたところ、「最近の子どもはそのような機会が逆に少ないので、全然OKです」との返事がありました。
このような未熟な、腹話術師とも言えない者に2年連続で声かけていただけたことで、年を重ねても頑張らなくちゃ、という思いを新たにしました。また、ゴスペル(神様の福音)を知恵を用いて語り続けることの意味と、神様からの使命がまだまだあるのだと思わされました。
続けること。やめないこと。上記の聖句の通り、歩き続けること。それがイエス様の尊い命の代価をもってクリスチャンとして召された者の日々の歩みであると同時に、ゴスペル腹話術に加えていただいた者の歩みであると思っているところです。